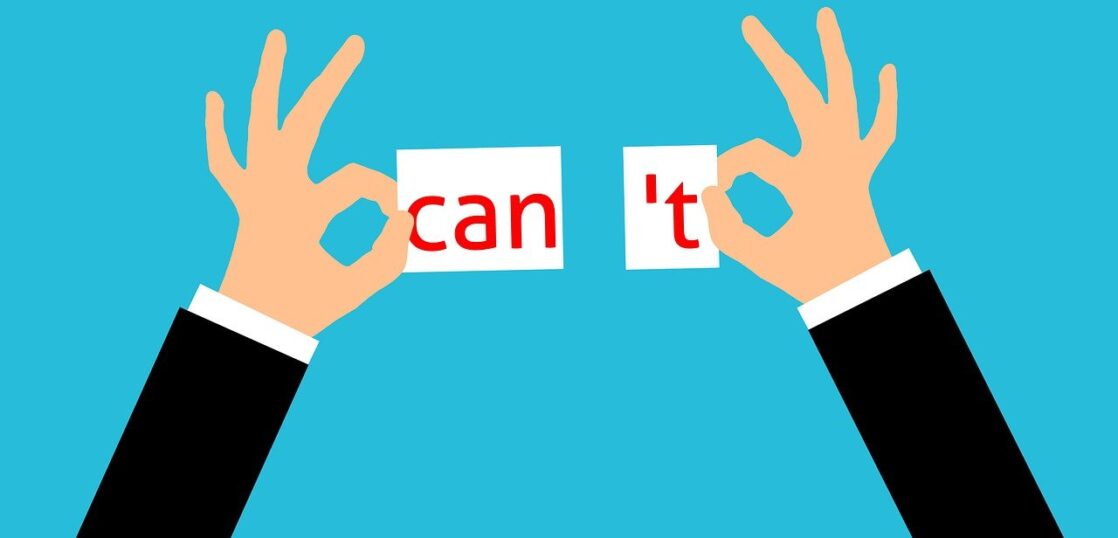ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。
近年、日本の物流業界にて長時間労働、厳しい取引環境、人手不足など課題が深刻化していることはニュースなどでご存じのことかと思います。
いわゆる、「物流の2024年問題」です。
残業時間規制及び拘束時間規制による物流への影響が懸念されています。特に長距離輸送においては、これまでと同じ運行方法では改善基準告示違反となる場合があります。
この問題に対処するために政府は、2023年6月2日に「物流革新に向けた政策パッケージ」を決定しました。今回は、具体的な施策としての「特殊車両通行制度の見直し」と今後の取り組みについてご紹介したいと思います。
特殊車両通行制度 とは?
道路法 車両制限令に基づき、一定の大きさや重さを超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の通行許可または通行確認が必要となっております。この制度が「特殊車両通行制度」です。
ドライバー不足の解消や働き方改革の実現のため、特殊車両通行制度を見直し、通行時間帯状況の緩和等を行うとともに、手続き期間の短縮を図るため、道路情報の電子化の推進等による利便性向上を図ろうとしています。
第23回物流小委員会-42-1-1024x724.jpg)
通行時間帯状況の緩和
現在、「特殊車両通行制度」では一定の条件を超える場合は、渋滞抑制や対向車・歩行者・自転車等との接触リスク低減の観点から、夜間(21時~6時)の通行が義務付けられています。
2019年6月に夜間通行条件が付される区間が全経路から特に交通への影響が大きい必要最低限の区間へ緩和されました。
第23回物流小委員会-43-1024x724.jpg)
ドライバー不足の解消や働き方改革の実現のため、道路の構造上の保全及び交通の安全の確保を前提に、通行時間帯条件の緩和が検討されています。
2024年4月より限定的な条件で緩和の試行が予定されています。
第23回物流小委員会-44-1024x724.jpg)
手続き期間の短縮
ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展により、 特殊車両通行の許可件数は大幅に増加しています。この申請件数の増加に伴い、特殊車両通行手続きの審査日数が長期化し、迅速化の取組を行い、少し短縮されましたが、限界があるという状況となっていました。
このような状況を踏まえ、「制度の抜本的な見直し」が実施されました。
第23回物流小委員会-45-1024x724.jpg)
「制度の抜本的見直し」が2022年4月から運用が開始された「新たな特殊車両通行制度の導入」です。
新制度は、「特殊車両通行確認制度」と呼ばれています。
新制度では、車両の登録は1回のみで、電子データ化された道路については、経路の検索から即時、通行可能な経路が回答され、通行が可能になるというものす。
第23回物流小委員会-46-1024x724.jpg)
しかし、この新制度には「課題」があります。
対象となる経路が電子化された道路情報のみとなっており、現状は利用可能な経路が少なく、さらに手数料が従来制度より割高であるので、新制度の利用が低迷しています。
第23回物流小委員会-47-1024x724.jpg)
新制度に関して、物流事業者や行政書士から以下のような意見や要望がでており、利用促進のために改善が必要な状況となっています。
第23回物流小委員会-48-1024x724.jpg)
新制度の利用促進に向けた取組
新制度の利用促進のために大きく2つの取組が行われています。
1.道路情報の電子化
道路情報が電子化されていない道路のうち、重点的に電子化すべき経路を特定し、2026年度までに電子化を実施。2027年度以降も、新たに発生する経路の電子化を継続実施。
2.新制度の利便性向上
検索条件の改善や利用可能車両の拡大、システムUIの改善など新制度の利便性向上を図り、割高感の解消。
2つの取組のうち、「新制度の利便性向上」については、利便性が向上すれば割高感が解消されるというロジックがイマイチ理解できませんでした。業務内容を簡潔にして手数料を下げるべきなのではないかと個人的には思いました。
第23回物流小委員会-49-1024x724.jpg)
今後の方針について
今後の方針については、上記で書いた「新制度の利用促進に向けた取組」を順次実施していくとのこと。
第23回物流小委員会-50-1024x724.jpg)
今回は、「物流の2024年問題」 の具体的な施策としての「特殊車両通行制度の見直し」の課題と今後の取り組みについてご紹介しました。
いくつか課題はありますが「特殊車両通行制度の見直し」は、ドライバー確保や働き方改革の実現のために必要性が大きいので、改善が進むことを期待しています。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。