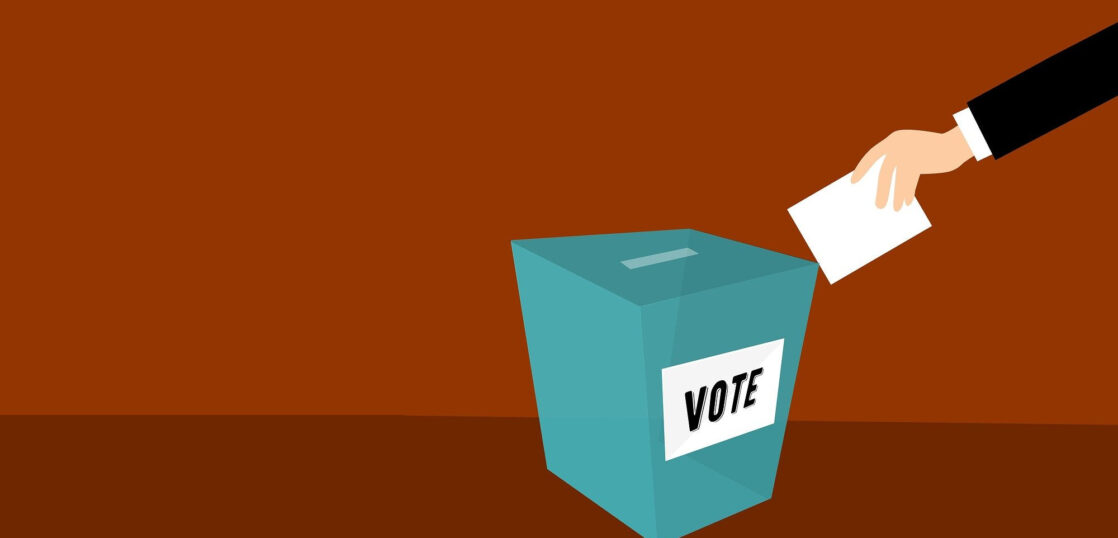ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。
第50回衆院選が2024年10月15日に公示され、10月27日に投開票となりました。衆院選は小選挙区289、比例代表176の計465議席が争われます。
気になるのは、主要政党の
「高速道路」や「物流・交通」の政策がどうなっているのか?
ですが、各党が出している公約や政策パンフレットからわかる範囲でご紹介したいと思います。
公示前勢力は、与党側が、自民党256、公明党32の計288議席。
野党側は、立憲民主党98、日本維新の会43、日本共産党10、国民民主党7などとなっています。
※ 本記事では公示前勢力で5人以上の衆議院議員がいる政党を主要政党と表記
自民党
- 国民の生命と暮らしを支えるとともに、我が国の経済成長を後押しする着実な道路整備・管理の促進に向け、必要な予算と財源を確保し、災害に強い道路ネットワークの構築や自動運転の実装、無電柱化、交通安全対策、自転車利活用等の取組みを持続的かつ計画的に推進します。
- 現場の実態を踏まえ、モーダルシフトの推進、荷主の強力・理解を得ながら、物流DX・GXの標準化をはじめとした物流効率化や価格転嫁、トラックGメンの強化や多重下請け構造の是正、消費者の行動変容を促す仕組みの促進等、国民生活を支える物流機能の強化を図ります。
- 全国で自動運転車やドローンの自動配送等のデジタルを活用したサービスの活用を急ぎ、人手不足などの社会課題の解決に取り組みます。企業や業種を横断して、データやシステム連携を行うためのプラットフォーム構築を推進し、DXを通じた社会課題の解決とイノベーションを後押しします。
公明党
- 鉄道やバスなど公共交通事業者の担い手確保や省力化投資等を支援するとともに、自動運転やMaaSなど交通DX・交通GXや地域の関係者の共創(連携・協働)を推進し、地域公共交通計画のアップデートや関係府省庁による重点的な支援を図り、地域公共交通の再構築を加速します。
- 2024年4月から開始された「日本版ライドシェア」や「公共ライドシェア」の実施効果を丁寧かつ継続的に検証するとともに、観光地や都市部等において配車アプリの普及やキャッシュレス設備の導入等を促進し、国や自治体、交通事業者等とも連携しながら「交通空白」の解消に向けた取り組みを強力に進めます。
- 持続的な賃上げの実現に向けて、事業者が人手不足の中においても生産性を向上させ、収益力を拡大していけるよう、省力化や自動化などのDX化投資を強力に支援します。
立憲民主党
- 道路整備に際しては、ミッシングリンクの解消など、地域が活性化するための道路ネットワークを構築します。
- 高速道路の利便性を向上させ、利用を活性化させることは、一般道や生活道路の渋滞解消による環境改善、そして新たな経済効果を生み出すことから、適切かつ計画的な道路の補修・建設を進めるとともに、簡易な出入口の設置を促進します。
- 高速道路の活用を促す料金制度を検討し、地域の活性化、物流の効率化、財政の健全化の視点とともに、維持更新に必要な財源の捻出、公共交通への配慮と支援をしっかりと行い、地域の活力・日本経済の活性化を図ります。例えば、償還期間の延長や、金利は実勢を踏まえた形に低減させること等により、料金体系を見直します。
- 改正物流関連法に基づきさらにモーダルシフトを進め、エコで安全な交通・物流が整うよう、陸・海・空の交通・物流の安全事業規制の見直し・強化を行います。
日本維新の会
- 世界的な開発競争が生じている自動運転の国内技術発展を支援し、レベル5(完全な自動運転)の公道実験の推進等により早期の実用化を図ります。
- 基礎自治体の域内交通について、法規制等の権限と財源を国から地方に移譲し、都市部における自動車専用高速道路の整備や、地方部における小型モビリティの規制緩和など、地方自治体が各々の地域事情に応じて域内交通を最適化する取り組みを加速します。
- ライドシェアを含む複数の交通サービスをITで統合し、一括して予約・決済する仕組みを導入するなど、MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)をより一層推進します。
日本共産党
- 生活密着型公共事業への転換をすすめ、保育所・特別養護老人ホームの建設、学校・福祉施設の耐震補強、道路・橋梁の維持補修、個人宅の耐震補修・リフォームなどを支援し、中小企業の仕事と雇用の増加につなげます。
国民民主党
- 高速道路料金について、補修費や建設費も考慮に入れながら、償還期間や金利を実態に合わせて見直すこと等により、上限設定(定額制)など新たな料金体系を検討します。また、スマートインターチェンジ等の簡易な出口を多く設置し、利便性を向上させます。ETC2.0の利用促進による高速道路の有効利用を進めます。
- 完全自動運転EVの巡回バス・乗用車を実用化し、及び地域公共交通システムを構築するスタートアップ企業を優遇します。交通事故の削減、高齢者等の移動支援や渋滞の解消などに資する自動運転の実現に向けて、特定条件下における完全自動運転(レベル4)を可能な限り早期に実現します。その実現に向けた道路の高度化と安全な交通社会の推進に取り組みます。
- 不公正な取引慣行を改善します。公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の産業界への周知・浸透・厳格な履行、悪質事例・好事例の公表を行います。運送業に係る「標準的な運賃」を確保した荷主への税優遇を行います。
- 下請法の適用拡大(資本金3億円以下から1千万円超)を行います。下請法・独禁法の罰則、優越的地位濫用の課徴金強化、公取等の取締強化、不適切事例公表・改善を行います。適正な価格転嫁を支援するとともに下請けGメン、トラックGメンを増員し取引の実態把握を加速させます。運輸業や建設業の「2024年問題」や構造的課題の解決に向け、改正物流関連2法や改正建設業法の着実な実行とともに、多重下請け構造の是正、適正取引推進等商慣行の見直しを行います。
公約や政策の中から交通や社会整備、物流に関する部分をピックアップしました。それぞれ各政党ごとに政策ボリュームや方向性、濃淡が違うかと思います。参考になれば幸いです。
民主党政権時の「高速道路の無料化」のような政策を訴えている主要政党は今回の衆議院選挙ではありませんでした。
2008年~2011年の高速道路の「休日1,000円」と「無料化実験」を覚えておられる方も多いかと思います。
最終的には廃止・凍結されることになった政策でしたが、当時の民主党政権は、無料化実験や料金割引の評価、将来の料金制度のあり方について検討するために「高速道路のあり方検討有識者委員会」を2011年4月に設置しました。
有識者委員会は、2011年4月から15回にわたり議論を重ね、最終とりまとめとして2011年12月に「休日上限1,000円は激しい渋滞発生や他の交通機関への影響などが問題であり、無料化は持続可能性がない」と国土交通大臣に答申を行いました。
上記の答申を踏まえ、3年後(2014年)に料金割引の財源がなくなるまでに、既存の料金割引を具体的にとりまとめて、2014年度以降の料金施策が決められることになりました。
その後、この流れを受け、2024年現在も高速道路に関する政策を調査・審議している「国土幹線道路部会」が2012年7月13日に立ち上げられます。「国土幹線道路部会」については以下の記事で詳細に解説していますので、ご覧下さい。
そして「国土幹線道路部会」にて2014年度以降の料金施策が検討され、2013年6月25日に国土交通大臣へ「中間答申」が行われ、2014年4月から実施され、現在も実施されている「全国の新たな料金体系の導入」へとつながります。
現在の高速道路の料金割引がどのような流れで決まったのかについては以下の記事で詳細に解説していますので、ご覧下さい。
今回の衆議院選挙における各党の政策を見ると、基本的には必要な道路整備を進めつつ計画的な補修を行っていくという部分はほとんど同じで、料金体系について濃淡があるといった印象でした。
ちなみに、2023年5月31日に成立した「高速道路の料金徴収期限を2065年から2115年へ50年延長する法律」の各政党の賛成・反対は以下のようになっていました。
- 賛成:自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党
- 反対:立憲民主党、日本共産党
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。